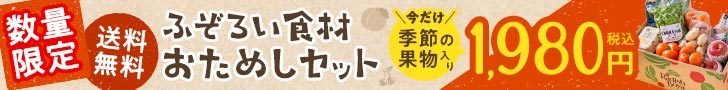トイトレが進まない!原因と対策まとめ【発達特性のある子にも効果的な工夫】
作業療法士*てつ先生
2025/11/04

トイレトレーニング(トイトレ)は、子どもが自立に向かって成長していく大切なステップの一つ。
しかし「なかなか進まない」「嫌がってしまう」と悩むご家庭も多いのではないでしょうか。
特に発達特性(自閉スペクトラムやADHDなど)のあるお子さんの場合、トイトレが思うように進まない原因がいくつも重なっていることがあります。
今回は、作業療法士の視点から「トイトレが進まない原因」と「できるようになるための工夫」をわかりやすく解説します。
目次
- トイレトレーニングが進まないのはなぜ?
- 発達特性がある子どもに多いトイトレのつまずき
- 平衡感覚や姿勢の悪さが排泄に影響する!?
- トイトレが進まないときに試したい工夫
- トイトレ成功のカギは「段階づけ」と「成功体験」
- まとめ|焦らず、子どものペースで一歩ずつ
トイレトレーニングが進まないのはなぜ?

トイトレの一般的な開始時期と難しさ
一般的にトイレが一人でもできるようになる時期は、幼児期(1歳~3歳頃)とされています。しかし、なかなかうまくいかない事も多く、トイトレに関する相談や悩みは多いです。
子どもにとっては「大きな変化」であることを理解しよう
赤ちゃんの頃は、生まれた時からおむつをつけて生活をしていますが、いつの間にかおまるに座ることを求められ、トイレという場所で排泄することを求められてしまいます。子どもの視点から考えると、今までおむつでしてよかったのに、急にトイレでの排泄を求められるので、これはとても大きな変化だと思います。
さらに、身体に常におむつをつけている身体感覚や視覚的な情報が突然なくなり、トイレでの排泄を求められるため、どのお子さんでも最初はトイレの失敗が見られることが見られると思います。でも、これは正常なことです。お子さん達は、まだ身体がトイレをする動きに慣れていないからです。
発達特性がある子どもに多いトイトレのつまずき

トイレがすすまない原因は多岐にわたり、特性によっても様々です。
模倣が苦手なタイプ(自閉スペクトラム傾向)
例えば自閉傾向がある場合は、周りの人達が行う行動に興味を示したり、模倣することが苦手な場合があり、日常生活動作を模倣するという学習機会が難しくなることもあります。
そのため「周りがトイレに行くから自分も行こう」という社会的模倣が起こりにくく、習得に時間がかかることがあります。
忘れやすい・集中しづらいタイプ(ADHD傾向)
ADHD傾向のあるお子さんは、その特性により、トイレに関する動きを忘れてしまったり、お尻を拭き取る事が雑になることがあります。
手順を視覚的に示したり、タイマーで声かけするなど「見てわかる工夫」が効果的です。
感覚の過敏さや鈍さによる影響
音に対する過敏さや嗅覚の過敏さがあり、その影響からトイレの入室を嫌がる場合もあります。最近は自動洗浄トイレやエアダスターの音のせいで外出先ではトイレに行けないという事例も聞かれます。
そして、それとは逆に、身体の感覚が鈍いために、おむつが濡れり汚れたりしてもお子さんの反応が見られなかったり、不快に感じることもないためそのままオムツに溜まる事に繋がる場合もあります。
食事・水分摂取の偏りが排泄に影響することも
水分をあまり取らなかったり、食物繊維の少ない食事が続くと、便秘など排泄リズムの乱れを起こすことがあります。
トイレトレーニングを進めるうえでは、食事・水分・生活リズムも整えることがポイントです。
平衡感覚や姿勢の悪さが排泄に影響する!?

便座に座るときの不安感
便器は大きな穴が開いていますよね。子どもにとってその上に座る事は大変なことだと感じます。子どもの平衡感覚が悪い場合は、座る姿勢の不安定さが生じてしまい、それに起因する不安から便座に座ることをためらってしまう場合もあります。
足がつかないことによる姿勢の不安定さ
さらに、便器に座る時に床に足がつかず、姿勢の不安定さが増すことも考えられます。
このような時は足台を使って安定した姿勢をとることで、安心して座れるようになります。
このようなことから、運動機能の未熟さからもトイレがすすまない原因となる可能性があります。
トイトレが進まないときに試したい工夫

トイレがすすまない時に行う工夫は様々な方法があります。その中でも私が意識している事は、「段階づけ」です。徐々にトイレに近づけながら排泄ができるようになり、最終的にはトイレで排泄できることをゴールとします。
ステップ① トイレに近い場所で安心して排泄できるようにする
まず初めに、トイレに入らなくてもいいのでトイレのある場所の前や近くなどで、おむつの中に排泄することを誘導!
よく、排泄時、部屋の隅や目立たない場所で排泄する子がいますが、これはそういう場所が本人にとって安心してできる空間ととらえます。なので、トイレに近い場所に安心できる空間を作ってあげることでトイレという場所に近づけるきっかけになると考えられます。
ステップ② トイレと排泄を結びつける練習をする
トイレに入ることができない場合は、トイレに少しでも入ることができるきっかけが必要!
トイレの中におむつを置き、子供の排泄前にそのおむつをお子さん自身に取ってきてもらうなど、排泄とトイレを結びつけます。好きなキャラクターのシールなどをトイレの壁などに貼ったり、トイレに座る事ができるごとにシール集めをするなど、お子さんのモチベーションに繋げることやトイレが心地良い空間にするなどの工夫もできます。
ステップ③ トイレでの一連の流れを一緒に練習する
排泄から後始末までの一連の流れを一緒にやってみる!
おむつでうんちなどをした後に、そのうんちをトイレで流すところを一緒に見る→お子さんにレバーを操作してもらい、実際にうんちを流してもらう→トイレのそばでお尻を拭く→トイレの中でお尻を拭くと徐々にトイレ内で各工程が出来るようステップアップしていきます。
トイトレ成功のカギは「段階づけ」と「成功体験」

トイレトレーニングに大切なことは、無理にお子さんに嫌な事を強制させないことだと思います。そして、トイレトレにたいして、段階づけの関わりが成功体験への鍵だと私は感じます。
例えば、野球をはじめたばかりの人が160km近いボールを投げられるわけがなくて、少しずつ基礎的な練習を続けることで徐々に上手にボールが投げることが出来るようになっていきますよね。
トイレトレも同じことが言えるのではないでしょうか。
まとめ
今回は、私の経験や知識をもとにした内容ですが、トイレトレにはたくさんの工夫や方法があると私は感じます。記事を参考にしていただきつつ、お父さんやお母さんの考えるアイディアも専門家を唸らせる方法があると思いますので是非一緒に考えてみてください!そして、子どもと思いやりをもって関わることが成長の第一歩になると思います!

作業療法士*てつ先生
経歴:作業療法士歴11年
作業療法士として働いています!
感覚統合や運動療法、作業活動などを通して、子供達が楽しく成長出来る事を目指して日々努力しています。