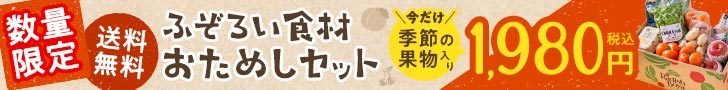スプーンを使わないのは発達の遅れ?手づかみ食べの時期と支援方法を専門家が解説
作業療法士*てつ先生
2025/11/11
はじめに

お子さんがいつまでも手づかみ食べを続けていると、「そろそろスプーンを使わせた方がいいのかな?」と不安になる保護者の方も多いのではないでしょうか。 特に発達特性があるお子さんの場合、スプーンやフォークの使い方がうまく身につかない背景には、感覚や筋力の発達、環境、成功体験の少なさなど、さまざまな要因が関係していることがあります。
今回は、お子さんに対する食事に対する支援の経験を通して、手掴み食べばかりしているお子さんに対する工夫や対策をご紹介していきたいと思います。
目次
手づかみ食べはいつまで続くの?

手づかみ食べの一般的な時期と発達段階
乳幼児期の子どもは様々な経験を通して、心身を発達させる事が大切だと言われています。その中でも食事は、とても大切な日常活動の1つです。食事は心身面だけではなく、他者と一緒に食べる場面を通して、コミュニケーション能力や社会性を育てれる時間にもなります。
しかし、発達特性により偏食傾向などがあり、食事に対する意欲が低くなってしまい食事に対して「楽しい」「食べたい」と意欲的に思えないケースもあります。今回は、お子さんに対する食事に対する支援の経験を通して、手掴み食べばかりしているお子さんに対する工夫や対策をご紹介していきたいと思います。
スプーン・フォークを使い始める目安は?

乳幼児の成長過程としてだいたい手掴み食べは6か月頃から始り、1歳頃からスプーンやフォークを使い始めます。1歳頃の手の機能としては、小さい物を人差し指と親指で摘まめるようになってきます。
発達特性がある子の場合の違い
私の支援経験の場では、手の機能が十分に発達しており、スプーンを口元に動かすことができるにもかかわらず、1歳を過ぎても手掴み食べをしているお子さんをよく見かけます。発達障がいのお子さんは、手の機能が遅れている事も原因として考えられますが、それ以外にも心理的要因や食事環境など様々な要因が原因として挙げられます。
スプーンやフォークを使わない原因とは?

過去の「うまくできなかった経験」が影響しているケース
スプーンやフォークを使った食事に対するモチベーションが低い可能性があります。
要因として、過去に自分スプーンを使って食べようとするも、上手く出来ずに口に運ぶ事も出来ないなどの「成功体験」を得られなかったため、お子さん自身が「自分で食べるよりもお母さんに食べさせてもらった方が食べられる」と感じている事も考えられます。
また、上手く操作できずに食べられない為、食べさせてもらう方が食欲を満たされると感じていることも考えられます。
低緊張や指先の力の弱さなど身体的要因

お子さまの身体症状の中でも「低緊張」と呼ばれる症状があり、筋肉を持続的に動かす事が難しい場合があります。
スプーンやフォークを口元に動かす時は、腕の筋肉は常に力を入れている状態にあります。さらに、身体の姿勢を安定させるために体幹の筋肉も常に力が入っています。低緊張の症状により、食べ物や食具を手に持って、口元に運ぶという動きは、お子さんにとって身体的な負荷になっている可能性が高い事も考えられます。
また、指先の力が弱いと指先でつまむ事が苦手であり、スプーンやフォークを手で固定することも難しい動作になっている可能性もあります。
利き手が定まらない・両手の協調が難しいケース

あまり意識されることが少ないですが、スプーンを持っていないほうの手で食器を持つことはとても重要です。
利き手が定まっていない場合は、スプーンやフォークの使い方も上手くできません。また、手で器をもって食べない場合は、口を器に近づけて食べる「かき込み食べ」になってしまいます。
そのような食べ方では、姿勢が悪くなり、一口の量の調整も難しくなり丸のみになってしまう可能性もあります。
手づかみ食べばかりの子にできる支援と工夫

「スモールステップ」で食具に慣れる練習法
フォークやスプーンを上手く使えない子供に対する工夫として、私が実践している方法をご紹介していきます。とにかく意識していただきたいことは、「スモールステップ」です。
- お子さんには食具を手で持ってもらう。
- 大人の手で包み込むように握り、一緒にスプーンを操作する。
- 1~3口、一緒に操作して口に運んであげて成功体験を積む。
- スプーンを動かす方向を誘導し、食べ物を救う経験を積める環境を作る。
- 1~3口程手伝って食べる事ができれば、後は手掴み食べでもOK。
成功体験を積ませて「できた!」を増やす
徐々に食具で食べる量を増やしていけたら良いですね。その過程を繰り返し、慣れてくれば大人の手伝う量を減らしていきます。最終的には、1人でも食具を使えるようになるのが理想です。
もし、お子さんが食具を持つ事を嫌がる場合は、無理は不要です。一口でも手伝って食べる事が出来ればOKです。
大事なことは、成功体験を積む事と継続です!
滑り止め食器など環境を整える工夫
両手が上手く使えない場合や利き手が定まっていない場合は、すべり止めがついた器やすべり止めマットを利用するといいです。食事環境を整える工夫もしてみましょう。
「自分でできた!」が育つとき

成功体験が自己肯定感を高める理由
自信を子供が持つことで、食事が楽しく感じると思います。食事という行為は、お子さん自身の成長を促すうえで欠かせない日常生活動作です。また、他者とのコミュニケーションをとる「社会性」や「精神面」の成長においても不可欠な活動だと考えられます。
療育現場での実践例と変化
私自身の療育でも、大人がお子さんと一緒に食具の操作を手伝ってあげることで、実際の操作する動きを感じてもらいながら成功体験を積み、自己肯定感を高めて食事が楽しいと思えるようにお手伝いをしています。
「食べたい気持ち」を大切にした関わり方
「手掴み食べ」はスプーンなどの操作が確立するまでは一般的に見られる行為でもあります。スプーンやフォークが使える時期が遅くても、お子さんの「食べたい」という気持ちを大切にして、好きなように食べさせてあげる事も大切です。
まとめ|焦らず、信じて、見守ることが一番の支援

発達のスピードは一人ひとり違う
私が日々の業務を積み重ねていくうちに、ふっと気付いたことがありました。それは、「子供は必ず成長していく」ということです。
「あの子は靴を一人で履けない」と言われていた子をこっそり影から見ていたら一人でも靴を履ける事が出来ていたのです。
びっくりです(笑)
私達療育者が温かく見守っているだけで、お子さんは日々成長していくのです。
親も子も無理をしない「成長を待つ」姿勢を大切に
療育者の支援によって成長することもあります。しかし、他の子よりも発達が遅れていると心配するよりも、発達の早さはお子さんによっても違いますし、心配をしなくてもお子さんは必ず成長してくれます。
この記事を参考にしながらお子さんを気長に見守る気持ちでお子さんを見守っていただけたらと思います。

作業療法士*てつ先生
経歴:作業療法士歴11年
作業療法士として働いています!
感覚統合や運動療法、作業活動などを通して、子供達が楽しく成長出来る事を目指して日々努力しています。